
睡眠環境診断士の内容と資格取得方法
睡眠というのは、その環境にも左右されることが多く、環境が悪く熟睡できないという方もいます。なんとなく枕を変えてみたりと、あまり睡眠に関する知識がないままその睡眠環境を改善しようと行なっても、改善されているのかどうか、よくわからず、熟睡もできているのかどうか、不明という場合も多いです。
やはり、熟睡を行うためには、その環境について考える場合は、科学的な観点から考える必要があり、睡眠に関する知識も求められます。そこで睡眠に関する環境を、総合的な観点から診断するのが、睡眠環境診断士の資格なのです。
睡眠環境診断士とは?
睡眠時に影響する要素としては、人体の皮下に、寝室環境、寝具とこの3つがあります。そうして、睡眠環境を快適で健康にするためには、以下のような課題があります。
・寝具の性能
・人の睡眠生理
・寝室環境
・人体と寝具のインターフェイス
・寝具と環境のインターフェイス
・人体と環境のインターフェイス
このような課題がありますが、これらは人体・寝具・環境と総合的に考えないとならず、これらのどれか1つに問題があっても、熟睡を妨げることになります。
そうして、人体・寝具・寝室のシステムとして総合的に理解できる人材の誕生が期待されているのです。人体、寝具、寝室環境についての知識を持ち、睡眠環境を、視察して測定し、調査して総合的に診断できるのが睡眠環境診断士となります。
今は人体・寝具・寝室のシステムとして総合的に展望し解説できる人物は少ない状況です。睡眠環境診断士では、学会の各分野の専門家に専門的分野からの知見を提示してもらい、これを集約して睡眠環境学として学問と技術を体系化することも目的としています。
学問を体系化することにより、「睡眠時の夜間の生活の質の向上」や「 寝具やインテリア、ホテルまたは旅館、住宅や福祉施設など、睡眠環境に関連する業界の活性化に繋がる基盤ともできるのです。
このような業界で、睡眠環境診断士は、睡眠生理学・寝具性能・寝室環境と3分野について知識を持ち、睡眠の環境を人体・寝具・寝室の総合的なシステムとして把握し診断や評価する役割を担います。どちらかというと、個人の睡眠環境よりも、業界の環境や製品について評価や診断を行なうような資格となります。
睡眠環境の学問
人体と寝具のインターフェイスに関するものには、眠る姿勢や寝具への体圧分布、床ずれ等などがあります。寝具と環境のインターフェイスでは、寝具の適応条件、室温や寝具の保温性などがあります。そして人体と環境のインターフェイスにでは、夏などの高温環境での睡眠、騒音環境の中の睡眠、夜行列車やバスでの振動中の睡眠と、生理学と環境工学に関する課題があります。
このような睡眠環境の学問は、本格的には研究されていないのが現状であり、体系的に考えると新しい課題も見えてきて、どのように改善し解決するかも見えます。
このような学問の進展には、睡眠での生理環境、寝具の環境と各分野の研究者や、関係する業務に携わる人々の努力や研究が必要なことは言うまでもないです。その他にも直接に自分自身の問題である生活者が認識を新たにすることもあります。
睡眠に関する学問を体系化するためには、睡眠生理や寝具、環境の各分野の研究者や企業担当者が、自身の専門に留まらずに広く理解する必要があります。そのような学問の研究や解明の一助となるためにも、睡眠環境診断士という資格はあります。
睡眠環境診断士となると、このような企業やメーカーの方のために、睡眠環境を理解するための講座などを開くこともあります。現在は睡眠環境診断士の資格を活かしての、専門的な職業はありませんが、ご自身の会社などの製品や環境の改善などにも役立てることができる資格です。
睡眠環境の課題
睡眠環境を改善するための課題としては、以下のように具体的にするとわかりやすく、把握しやすいです。
・寝具に関して
布団の性能の保温性や保湿性、耐久性や安全性、さらには価格などがあります。
・人体
寝具への体圧、眠る姿勢、体に関しての体温や発汗、呼吸などがあります。
・寝室
室温や保温性、気温や室温、さらには匂いや振動、音や明るさと、関係する要素は多数あります。
このようにして睡眠環境に関する要素は、3つに分けられますが、それぞれで関係する要素は多数あり、その施設の造りなどでも、関係する要素は大きく違ってきます。そのために、課題としては必ずしも、このような要素が重要だと、断定するのは難しく、個々のケースでそれぞれ対応して診断し、課題を見つけないとなりません。
また人は必ず睡眠を行ないますが、生活リズムやその人の健康状態なども、睡眠に関する課題として大きく影響し、こちらも必ずしもこの課題だと断定できません。
そこでその個々に関する課題を見つけ出し、明確にするのに役立つのが、睡眠環境診断士という資格であり、科学的観点から課題を把握していきます。
睡眠環境診断士の資格取得方法
寝具と人体、そして寝室の3つをテーマが、睡眠環境とどのように関係するのかを総合的に診断するスペシャリストがこの資格です。
・試験について
資格を取得するには睡眠環境講座という講座へ参加しないとなりません。開催期間は3日であり、最終日には認定試験がありますので合格すると、睡眠環境診断士の資格が得られます。
講座は年2回行なわれており、参加費は8万円、募集人数上限が各回30となります。参加費は8万円もかかりますので決して安くなく、気軽に取れる資格とはなりません。講座は定員になると、参加はできないので次回開催まで待たなければなりません。毎年睡眠環境講座の開催は2月から3月、そして8月から9月となっていますので、睡眠環境診断士になりたい人は早めに応募しましょう。
そして講座では、熱移動の基礎や体温調節系の機能などから、不眠と生活習慣病や寝具の性能評価について、寝室環境の調査方法、睡眠経過の調査についてなどを学びますたとえば、子供の集中力低下や突然キレることは、実は睡眠と関係しているという話も聞くことができます。快眠を得るには、室内温度や湿度をどれくらいに保つことがベストか、などということを科学や数学的な側面から学び理解していきます。
講座の期間は3日と短期講座になりますが、スケジュールはハードです。1日目は10時30分から始まり、1時間ほどの講演が17時30分まで行われます。2日目は9時から16時、そして17時から懇談会があります。最終日も9時からスタートし、15時までカリキュラムを進めていき、最後の16時から17時半に認定試験になります。講演の間には、休憩や食事休憩もあり、それを除くと朝から夕方まで椅子に座り講座業を受けます。
こうして最後の認定試験を受けると、その後日にちをおき、試験合格かどうかが発表されます。無事合格となると、睡眠環境診断士に認定され、資格を得られます。試験内容は受講者全員が合格することもありますので、それほど難しい試験ではなく、講座を受けてしっかり勉強すれば、合格できる範囲の内容です。
睡眠環境診断士は、いくつもある睡眠に関する資格ですが、その中でも睡眠に関わる企業やメーカーなどと繋がりのある資格です。その名前の通り、睡眠環境を診断する人となり、資格を取得するとなると、そのような内容を学んでいきます。個人でももちろん役立てられる資格ですが、やはり企業やメーカー向けという側面が強い資格です。
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)



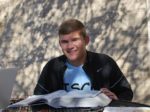




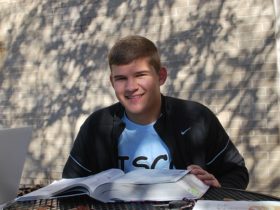









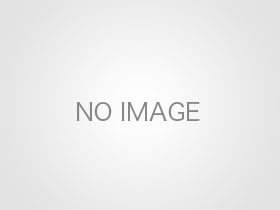









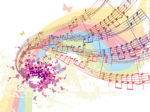













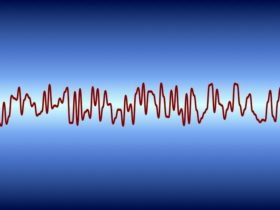




この記事へのコメントはありません。